こんにちは、香水ライターの凜です。
季節は香水の大祭典のあった先月から巡り、もうじき冬に差し掛かる11月になってまいりました。
肌寒くなってきておりますが、前回お伝えさせていただいた通り、香水が最も美しく香る時期であり、11月はクラシックコンサートが最も開催されるため、芸術の秋ならぬ音楽の秋としても相応しい季節でもあります。
特に、11月は翌月のクリスマスとも重なり、ベートーヴェンの第九が演奏される絶妙なタイミングです。

なので、今回はクラシック音楽の楽曲を作品全体で表現し、音色を香りと素肌で感じるフレグランスブランド「ラニュイパルファン」の作品を、セレスで取り扱っている8本すべて、クラシック音楽を添えてご紹介いたします。
(先月のサロンドパルファンでもラニュイパルファンは出展があり、先行販売した新作のピアノ協奏曲第1番(ショパン)と、この楽曲を味覚でも味わえるようショコラティエとコラボレーションをしたチョコレート、ラヴェルのラ・ヴァルスを私も個人的に購入しており、クラシック音楽を愛するものだからこそ出せるそのクオリティと魅力にはいつも驚かされます)
ラニュイパルファンとは?ブランドの秘めたる魅力をご紹介
ラニュイパルファンとは、冒頭でも少しお伝えした通り、クラシック音楽の楽曲を作品全体で表現するフレグランスブランドです。ブランドを立ち上げたのは海老原光宏氏ですが、彼は創業者でもブランドのディレクターでもなく、「コンダクター(指揮者)」です。ブランドを創業し、広告やパッケージデザイン、調香などを含めたプロジェクトの総指揮を演奏者(担当者)にするだけのみならず、現場に自ら立って顧客の声を聴いて接客もし、彼自身が全身全霊、ブランドそのものという音楽を表現していく様は、まさに「コンダクター(指揮者)」さながらです。

彼自身もピアノ演奏を趣味としており、クラシック音楽を人類が残した優れた遺産と考え、その素晴らしさを多くの人に届けたいと自費でブランドを立ち上げたほどの熱意、今までの音楽業界のようにクラシック音楽ファンをターゲットに活動するだけでは市場は広がらず、日常で使われるものと組み合わせていく必要があると戦略的な知性を持って、クラシック音楽を香りにしていく活動を「ラニュイパルファン」により始めました。

単に香りで楽曲を表現するのみならず、パッケージもピアノの黒鍵を再現しており、先日訪れたサロンドパルファンで包まれていた袋も「LA NUIT RECORDS(ラニュイ レコード)」と記されている現実のCDショップのパッケージを模したような遊び心もあり、調香師が調香時に楽曲を聴いて香りに再現することは勿論、初回限定盤にはピアニストによる楽曲の解説書も特典にされている徹底ぶりです。

香水のみならずインテリア用品や今年のサロンドパルファンではチョコレート(味覚)ともショパンの作品でコラボレーションしていた幅の広さもあり、ブランド名も「管弦楽の魔術師」と称えられて、オーケストラで表現するオーケストレーションの稀代の天才たるモーリス・ラヴェルの代表曲「夜のガスパール」より冠された「ラニュイ」というこだわりぶりで、私も大好きなフレグランスメゾンの一つです。
⏱️ Celesの全ての香水が300円OFF!⏱️
12月31日まで
クーポンコード:yj9s
※他のキャンペーンと併用できます。
※初回限定、送料には適用できません。
1,500種類+から選び放題❤️
Celes公式サイト>>
ラニュイパルファンのオーデトワレ8作品による「クラシック音楽の旅路」をご案内
今回、お届けするラニュイパルファンの作品はブランドのアイコニック的な作品であるラヴェルの「夜のガスパール3部作」から、ラフマニノフの生誕150年を祝して創られた「ピアノ協奏曲第3番」に、彼の同級生であり、独自の神秘主義と象徴主義を極めたロシアの作曲家スクリャービンの「黒ミサ」、「白ミサ」、「炎にむかって」、「昆虫」です。
1.夜のガスパール第一曲 オンディーヌ(モーリス・ラヴェル)~ウォータリーフローラル~
香りのノート
Top
ウォーターアコード
Middle
スズラン
Last
スミレ
最初にご紹介するのは、ブランドを象徴するアイコニックフレグランスであるモーリス・ラヴェルの夜のガスパール三部作の一作品目、水の精オンディーヌの悲恋を描いたウォータリーフローラルの夜のガスパール第一曲 オンディーヌ(モーリス・ラヴェル)です。
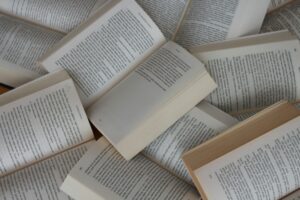
「夜のガスパール」は大詩人たるボードレールによって見出された名も無きフランスの詩人、ベルトランの作品ですが、シュールレアリスムのパイオニアとして芸術家から称えられ、 近現代の時代を橋渡しとしてクラシック音楽における重要な作曲家の一人であるフランスのモーリス・ラヴェルが音楽にして表現し、世に知れ渡りました。そんな夜のガスパールをラニュイパルファンはさらに香りで現代に表現するという時を超えたコラボレーションを果たしています。
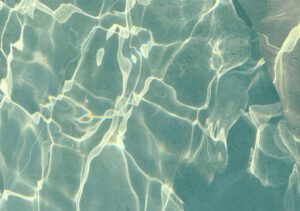
付けたてからすぐにウォーターアコードが織り成す、「水」そのものの香りが漂ってきます。フローラル感はまだ薄く、どちらかというと清浄な水の香りです。スプレーを吹きかけると霧のように湖に佇む水の精オンディーヌの香りが拡がるように感じます。
清らかなのにどこか切なくて物哀しい旋律を感じます。そして、楽曲のようにとても暗くて儚いそんな印象も受けます。ピアニストの指が奏でる滑らかな音が和音の構成音を一つずつ順に奏でるアルペジオと、同音もしくは複数の音を緻密に反復するトレモロの技法によって、水がきらめき変容していく様子を表していると言われています。

トップ、ミドル、ラストに分かれてはいますが、実はそこまで香りの大きな変化はなく、繊細にゆらぐように展開をしていきます。少し時間が経つと、ウォーターアコードに鼻が慣れていくからか、スズランとスミレによるフローラルノートが感じられていきます。華やかで女性的というよりは、清楚で儚く水に濡れた草花のようで、控えめでミステリアスといった表現が近いです。スズランやスミレはパウダリーフローラルの代表格ではありますが、ウォーターアコードのためか粉っぽさはあまりなく、瑞々しく清楚に咲いています。

ずっと嗅いでいると、オンディーヌが人間の男に恋をして、彼を誘惑しようと妖しく取り入ろうと囁き愛の告白をするも、彼は人間の女性に好きな人がいると伝えて、オンディーヌは失恋して、恨みがましく泣きながら嘲笑して独り水に飛び込んでいくという、物悲しさも憶えてくる絶妙さがあり、持続性がそこまで強くないからこそ、この儚い美しさを表現できるのでしょう。

夜のガスパール第一曲 オンディーヌ(モーリス・ラヴェル)は水の精オンディーヌの悲恋を描いた詩を美しい音楽で表現し、そこからさらに調香師が表現した時を超えた芸術作品です。扱われている二種類の花のうち、スズランの花言葉は、「純粋」、「純潔」、そして「幸福の再来」、特に舞台のフランスではスズランの日に贈ると幸運が訪れると大切な人に贈る習慣があり、スミレの花言葉はフランス語では、「私のことを考えて下さい」という言葉になり、オンディーヌの心情が自然と想像もできて、切なくも美しい物語の香りが手首から鳴り響きます。
2.夜のガスパール第二曲 絞首台(モーリス・ラヴェル)~スモーキーレザーウッディーシトラス~
香りのノート
Top
レザー
Middle
エレミ
Last
シダーウッド
2本目に続けてご紹介するのは、ブランドを象徴するアイコニックフレグランスであるモーリス・ラヴェルの夜のガスパール三部作の二作品目、静寂の夜に絞首台に吊るされる死体の様子を描写した不気味なスモーキーレザーウッディーシトラスの夜のガスパール第二曲 絞首台(モーリス・ラヴェル)です。

肌に付けると、革のレザーとスパイシーで温かみある樹木と言われるシダーウッドの温かさが皆無で、シトラスの香りと評される樹木エレミのシトラス的な明るさが極限までに抑えられた柑橘のグラデーションが、罪人が絞首台に向かう時の絶望と土埃の香りや鉛筆の芯のような無機質で金属っぽい香り、血の香りを表現したであろう鉄っぽい香り、「希望」や「明るさ」、「温かさ」といった概念の対極を行く、「絶望」、「暗さ」、「冷たさ」が押し寄せてくる、使う場所も付けるタイミングも非常に悩ましい作品です。

自室でピアニストによる絞首台の曲を聴くときに付けると、世界観に没頭出来て嗅覚でも絞首台の音色を体感できる何とも言えない気分になります。明るくて元気な時は勿論、雨が降った陰鬱な気分の時に、精神的に病まれている場合に付けるとどうにかなってしまいそうなほど完成度が高いため、健全なメンタルの時に使うことをおすすめします。

夜のガスパール第二曲 絞首台(モーリス・ラヴェル)は絞首台に吊るされた死体を描写した陰惨な様子を不気味な音楽で表現し、そこからさらに調香師が表現した時を超えた芸術作品です。本作について、散々ネガティブなことをお伝えしたと思いますが、深い闇の先には必ず光があります。眩いばかりの大きな光の影はとても暗いのと同じように表裏一体です。だから、吊るされた死体ということは、その人が生きていた時間もあったわけで、人生の時間と少し重く向き合いたい時にひっそりと付けるという使い方も良いでしょう。
3.夜のガスパール第三曲 スカルボ(モーリス・ラヴェル)~スパイシーオリエンタル~
香りのノート
Top
クローバー
Middle
ネロリ、スパイクナード
Last
オークモス
続けて3本目にお届けするのは、ブランドを象徴するアイコニックフレグランスであるモーリス・ラヴェルの夜のガスパール三部作の三作品目、真夜中の寝室で小鬼のスカルボが飛んだり跳ねたり、暴れまわってスッと消えていくのに翻弄されて不眠症に悩まされるホラー調を描写したスパイシーオリエンタルの夜のガスパール第三曲 スカルボ(モーリス・ラヴェル)です。

肌に乗せるとまず、トップノートに位置するクローバーの苦々しい草のグリーンさが押し寄せます。人によっては苔のように感じられる方もいるかもしれませんが、この苔の香りは樹木の苔であるラストに位置するオークモスが仄かに香っているかもしれません。すぐに後を追うようにミドルに位置するスパイクナードの激しいドライさや土っぽさと、微かな甘さもあるオリエンタルウッディーの洗礼を受けます。山椒の香りに感じられる方もいるようですが、スパイクナードは甘松(「カ」ンショウ)という別の植物の樹木です。

しかし、少し時間が経って、オレンジの花であるネロリの香りのフローラルな甘やかさが出てくると、スパイクナードのアーシーなスパイシーさと融合されて、不思議と山椒のような香りになっていきます。スパイシーでエスニックな山椒が肌の上から香って、いたずら好きの小鬼スカルボに翻弄されていると言っても過言ではないかもしれません。

次第に馴染んでラストになっていくと、オークモスのどっしりと構えた安定感ある香りと混ざり合って柔らかな余韻となり、どこか小鬼スカルボの影を感じながらもあれ消えた?といった感覚になっていると思います。ただし、絶妙にスカルボは存在してそうなそんな香りで、まさに小鬼スカルボに悩まされて不眠症になっている様子が浮かんできます。

夜のガスパール第三曲 スカルボ(モーリス・ラヴェル)は小鬼スカルボのいたずらに翻弄されて不眠症になっている人物のゴシック的なホラーな様子を超絶技巧のピアノ音楽で飛び上がるさまやどこか不気味にスタッカートが利いた激しさを表現し、そこからさらに調香師が表現した時を超えた芸術作品です。
夜眠る前にピアニストが奏でる超絶技巧のスカルボを聴くと、興奮してしまいホラーとは別の意味で寝られなくなって、さらに本作を手首に付けるともう安眠できる自信はありません。次の日が遠足でワクワクしている小学生に戻った気分になります。本作は他の夜のガスパールシリーズよりも日常的に使いやすい作品で、夜のガスパールでどの作品か迷ったらまずはこちらをおすすめします。
4.ピアノ協奏曲第3番(セルゲイ・ラフマニノフ)~フローラル~
香りのノート
Top
ベルガモット、ペッパー
Middle
ローズⅠ、ジャスミン、 金木犀
Last
ローズⅡ、オークモス
4本目にご紹介するのは、セルゲイ・ラフマニノフの生誕150周年記念を祝って捧げた、クラシック音楽界で三大協奏曲に数えられ彼のピアノ協奏曲で最高傑作と謡われており、ラフマニノフならではの重厚感が美しくて高貴な二種類のローズにジャスミンが使われたフローラルのピアノ協奏曲第3番(セルゲイ・ラフマニノフ)です。

肌に付けるとやって来るのは、大輪の真紅の薔薇とジャスミンが織り成す重厚感。豪奢で華やかな原曲そのものの香りが漂い、光が差すように感じるのは柑橘類のベルガモットが添えられているからでしょう。ペッパーのマイルドなスパイシーさも絶妙で、ワインやシャンパンの弾けるような優雅さを想起される方もおられるようです。また、ペッパーとベルガモットは眩い光を強調しています。だから、独特の高貴な神々しさが感じられ、天からさす救済のように思えます。

肌に馴染んでくると、ミドルのまろやかな金木犀の優しくて甘いノスタルジックな香りや、ラストのオークモスのしっとりと落ち着いた香りがグラデーションのように添えられていき、ピアニストの演奏さながらに香りでも余韻を楽しめる逸品となっています。

原曲は演奏者に技術的ならびに音楽的に課される要求の高さが大きいほか、身長が2メートルもあり、非常に手が大きく12度分の音階を押さえられた(多くの人が押さえられる限界は10度と言われています)作曲者ラフマニノフだからこそ成せる技法もあるという、生まれつきの手の大きさまで求められるピアニスト泣かせぶり。
原曲のカデンツァ(オーケストラや独奏において、伴奏一切なく演奏者単体が高度な技術を華麗に披露するための、曲の特定箇所に挿入されている部分)も壮大な幅で行き来する和音の連なりで、控えめなもの(通称小カデンツァもしくはオリジナル)と壮大なもの(通称大カデンツァもしくはオッシア)で二種類用意されているうち、前者を選ぶピアニストが発表当時は多かったと言われています。

だからなのか、ローズが1と2と分かれてミドル、ラストにそれぞれ二種類ブレンドされており、原曲の際の小カデンツァの繊細ながら洗練されていて気品あるさまと、大カデンツァの豪奢でダイナミックかつ華やかさが描写されている複雑さも兼ね備えているラフマニノフの150周年のお祝いに相応しい傑作に仕上がっています。

ピアノ協奏曲第3番(セルゲイ・ラフマニノフ)はその節目に相応しく、また晴れの場は勿論、クラシック音楽の演奏会に付けていけるような、クラシカルさがありつつも芸術的で人と被らない二種類の薔薇にジャスミンの華やかすぎるフローラルフレグランスです。特別な席でなくても自室で何か特別な良いことがあった時や、それこそ大切な節目に付けるのも大変素敵で、私もそんな折にひそかに嗜んでいます。
5.炎に向かって(アレクサンドル・スクリャービン)~オリエンタルハーバルシトラス~
香りのノート
Top
不知火(蜜柑)
Middle
イランイラン、パロサント
Last
パチュリ
5本目にお届けするのは、先のラフマニノフの同級生であり、19世紀から20世紀初頭にかけて活躍していたロシアの作曲家であるアレクサンドル・スクリャービンが最後に残した作品であり、晩年の独自の神秘主義に傾倒していた作風を闇から光(炎)に向かい、究極の癒しと救いにたどり着くよう表現した、火の国熊本名産の蜜柑不知火を筆頭に、太陽の花たるイランイラン、スペイン語で聖なる木を意味する南米や中央アメリカの香木パロサント、古から魔除けの儀式でも扱われたパチュリの厳選された4種類の香料を用いた、炎に向かって(アレクサンドル・スクリャービン)です。

付けると鼻腔に届くのは、和の柑橘不知火の酸味と苦みが混じった独特の香りと共に、どこか薬品めいたハーバルグリーンの香りです。薬草酒といった方が的確でしょうか。火の持つ温かみと清々しさを同時に感じられる調香です。

少し時間が経つと、パロサントの香木が薪となって燃え上っていく清らかなオリエンタルウッディーの煙が立ち込めていきます。イランイランも主張をし始め、本作では普段のイランイランならではの官能や色気といった女性的な要素は皆無で、どちらかというと神秘や神聖な火としての要素が強いです。聖火の灯とも言いましょうか。そして、そんな聖火の灯が焚かれていくと、それは自然とパチュリが奏でる聖なる儀式へと誘われます。

アレクサンドル・スクリャービンは、19世紀と20世紀の狭間に活躍したロシアの作曲家で、音楽院にてラフマニノフと同級生であったことは冒頭でも少しお話ししました。
スクリャービンとラフマニノフは対照的で、ラフマニノフが大男ということも一つ前の作品の解説で触れましたがスクリャービンは小男で、特筆すべきはラフマニノフが歴代音楽家のショパンやシューベルトに代表される情緒的なロマン主義の系譜を受け継ぎ、生涯をささげたのに対し、スクリャービンに関しては初期の頃は彼もそんなロマン主義の影響を強く受けていたものの、中期後期に至ってはロマン主義を脱し、そこから発展させた独自の彼ならではの、音と色を関連させる共感覚に基づいた神秘主義的な難解な作品を生み出してきたという部分です。だからなのか、スクリャービンの作品は神や天に救いを求めるような音楽にさえ聴こえます。

炎に向かって(アレクサンドル・スクリャービン)は、どこか神秘的な不可思議さがあって、聖なる火が焚きあがっていく様子を、自分だけの聖なる儀式をする時に自然と傍らに原曲の炎に向かってと同様に感じられるそんな作品です。ハーバルが強めなシトラスの香りでオーソドックスではなく、個性的なものをお求めの方にも一度はお試しいただきたいです。
6.ピアノソナタ第10番昆虫(アレクサンドル・スクリャービン)~スパイシーハーバルシトラスウッディー~
香りのノート
Top
グレープフルーツ
Middle
シダーウッド、スパイス数種
Last
ベンゾイン
6本目にご紹介するのも、19世紀から20世紀初頭にかけて活躍していたロシアの作曲家であるアレクサンドル・スクリャービンの作品で、頻繁に登場するトリルのくるくるとした技法から「トリルソナタ」とファンの間では親しまれ、彼自身は「光と昆虫のソナタ」とも呼び、「虫たちは太陽から生まれ、彼らは太陽の接吻なのである」と口にしていたほどで、本原曲もまた一つ前にご紹介した炎に向かって同様に晩年の神秘主義の影響が色濃く出ている、爽やかなハーバル(草)とスパイシーシトラス(光)とウッディー(樹木)がトリプルに合わさった表題らしい、代表作の一つであるピアノソナタ第10番「昆虫」(アレクサンドル・スクリャービン)です。

付けるといきなりスパイスとグレープフルーツのシトラスが織り成す、昆虫を引き寄せる魅惑的な光のパルスを感じます。ベンゾインの放つねっとりとした甘みも感じられて、中毒性も高く、クラフトコーラのような香りと例える方もいらっしゃるほどです。シダーウッドは温かみのあるスパイシー感ある樹木として知られており、そんなシダーウッドとスパイスの相性は言うまでもなく、ねっとりとした甘みのベンゾインと絡み合うことで樹木の樹液(昆虫にとっての甘い蜜)を表しているのではと感じました。

公式には使用されている複数のスパイスまで明かされてはいませんが、公式の説明文では月桂樹(ローレル)やカルダモンが示唆されており、確かに鼻をすませばカルダモンの甘さと相性抜群なあの香りや(材料にカルダモンが使われている甘いチャイの飲み物にレビューで例えている方もおられました!)、ハーブが香料に記載されていないのに葉っぱのような爽やかさがあるのは葉のローレルが使われているからだと考えればすべてが腑に落ちます。

自然界の温かみある陽光に、草木が生い茂るなか昆虫たちがくるくると生き生きとしながら飛び交い、愛を奏でていくそんなスクリャービンが言っていた「虫たちは太陽から生まれ、彼らは太陽の接吻なのである」という言葉の意味が解るような光景が浮かびます。
ピアノソナタ第10番「昆虫」(アレクサンドル・スクリャービン)はクラフトコーラが連想される爽やかで明るくてナチュラルな甘やかさの良いとこどりをしたような作品です。「昆虫」というタイトルに身構えて、青々しさや苦みの強い香りをイメージされた方もおられるかもしれません。しかし、実際にかいでみると爽やかなハーバルっぽさや温かみのあるスパイシーシトラス、草や木々のぬくもりや甘やかさと親しみやすさを感じるという良い意味で裏切られた方も多いでしょう。

ラニュイパルファンで現在執筆時点で4種類あるスクリャービンの作品から選びたい方へ、軽やかさがあるものをお探しで、香水を付けなれていない方でナチュラルに付けたいならば本作を是非お勧めします。甘めなスパイシー感がメインのため、ハーバル強めなものがお好みでしたら一つ前にご紹介した、炎に向かってが良いでしょう。
7.ピアノソナタ第7番白ミサ(アレクサンドル・スクリャービン)~オリエンタル~
香りのノート
Top
ベルガモット
Middle
セージ、ラブダナム(シストローズ)
Last
ミルラ
7本目にお届けするのも、19世紀から20世紀初頭にかけて活躍していたロシアの作曲家であるアレクサンドル・スクリャービンの作品で、彼が「白ミサ」と副題を名付けて特別に愛し、演奏会でも頻繁に弾いていた後期作品の一つで、後期作品らしい音と色を照らし合わせる共感覚を用いた独自の宗教色の強い神秘主義の反映を超えて、その集大成と言っても差し支えない、天上の神々に救いを求めて、法悦(エクスタシー)に達した歓びを表現した、白という色から連想される「清浄」や「神聖」が感じられる、清々しいセージと差し込む光のベルガモットが前奏を奏で、オリエンタルなラブダナムやミルラに昇華されていくような、ピアノソナタ第7番「白ミサ」(アレクサンドル・スクリャービン)です。

肌に乗せると、ベルガモットのシトラスめいた光のような香りが、清涼感というより清浄さを感じるハーバルなセージと共に降り立ちます。セージは古くから、中南米で浄化のハーブとして重宝されており、現代に至るまで浄化にと、お香のように焚く方もおられるほど清浄さを象徴する植物です。

オリエンタルなスパイシー感ある甘さを感じるのは、紛れもなくラブダナム(シストローズ)のものです。ラブダナム(シストローズ)という名前から、ローズ(薔薇)の親戚や仲間と思われる方もおられるかもしれませんが、全くの別物です。同じ花の仲間であることは間違いありませんが、こちらは花ではなく葉っぱからとれる樹脂を用いるため、アロマテラピーでは樹脂に分類される香りでフローラル感というよりも、オリエンタルでねっとりとした温かみのある甘さにスパイシー感も感じられる独特な芳香を放ちます。

重たいアンバーや動物的な香りに近く、官能的に感じられる香料ではあるのですが、本作の場合はそうした側面も確かに感じられますが、神聖な清浄さが保たれているため、セクシーな性的魅力というよりは人間の本能的な法悦への歓びです。かつて、キリストに捧げられた救済の香りとして名高いフランキンセンスやミルラの代用として扱われたことからも、どこか神秘的な雰囲気にも思います。

しばらくすると、先に申し上げたキリストに捧げられた救済の香りミルラが満を持して現れます。天に届くようにスモーキーな薄暗さをもって厳かに香ります。ミルラは樹脂の香りで重さはあるものの、やはり救済の香りだからか、神聖さが鼻腔に届いて教会にいるような厳粛な気持ちになっていきます。時間が経てばたつほど天に届くような清浄な香りになっていき、スクリャービンが愛した「白ミサ」に相応しい調香だと自然と思えます。

ピアノソナタ第7番「白ミサ」(アレクサンドル・スクリャービン)は神の救済や法悦など難しそうなことを考えずとも、日々の暮らしの中で気持ちの浄化をしたい、少し気分をリセットしたい、あるいは節目の大切な日だから、それこそクリスマスの朝だから、神聖な気持ちになりたいといった時に使いたくなるような、そんな作品です。対の作品である黒ミサと一緒に持たれるのもお勧めです。
8.ピアノソナタ第9番黒ミサ(アレクサンドル・スクリャービン)~オリエンタル~
香りのノート
Top
該当なし
Middle
アミリス、ラブダナム
Last
ベチバー
8本目にお届けするのも、19世紀から20世紀初頭にかけて活躍していたロシアの作曲家であるアレクサンドル・スクリャービンの、彼自身が副題を名付けて特別に愛した「白ミサ」の対となる作品で、対照的に彼の友人が「黒ミサ」と副題を名付けました。
白ミサ同様に後期作品の一つで、後期作品らしい音と色を照らし合わせる共感覚を用いた独自の宗教色の強い神秘主義の反映を超えて、その集大成と言っても差し支えない曲です。ただし、その本質は神聖な白ミサとは対極です。黒ミサとは欲望を叶えるための神を冒涜する、悪魔崇拝の儀式のことで、原曲のおどろおどろしささながら、本作も通常はあるはずのトップノートが存在しない異端の構成となっており、どこか不気味な不協和音が聞こえるような重くて暗いオリエンタルのピアノソナタ第9番「黒ミサ」(アレクサンドル・スクリャービン)です。
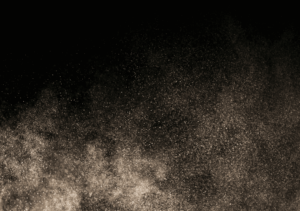
肌に乗せると、埃被ったような土の匂いが漂います。暗くて光どころか何も見えず、不協和音が静かに鳴り響いていくような不気味な音楽が鳴っています。トップノートが存在しない構成のため、当然、親しみを感じさせる明るさあるノートや、通常はトップに来るシトラスは介入する余地はなく、他のトップに来ることが多い爽やかなハーブや軽やかホットなスパイシーも存在しない。
香水に触れて早、15年近く経ちましたが、シングルノートではない通常の3層のノートに分かれているフレグランス作品で、トップノートが存在しないものは初でした。当たり前のように存在するトップがないだけで、こんなにも重たく、暗く、そして非日常的になってしまうのか、と黒ミサを身にまといながら思いました。ただし、私はこの黒ミサの香りが大変好きです。
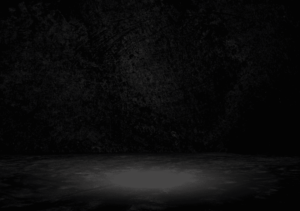
何故ならば、スクリャービンの遺した黒ミサという、希望や救いという概念は一切なく、むしろ神聖さをどす黒く塗りつぶしたような闇の曲を表現するためとは言え、本作品以外私の知る限りではトップノートに何も入れない調香の作品がないほど、今までの既成概念を壊すほどの覚悟、そして何よりもあまりに美しい静かな暗闇の香り。使われているものもたった3種類の香料で、それぞれが美しく重なる旋律のような部分が大変素晴らしい。

先に述べたベチバーはアーシー(土っぽい)で人によっては焦げ臭さや埃被った強烈な匂いに感じる方もいるベースノート(ラスト)で用いられる香りですが、これが作品全体の暗さや落ち着きに貢献しており、次にウッディー調の香りで松明にも用いられて、蠟燭を消した時の焦げ臭さ香る植物アミリス。闇の儀式に使われる蠟燭の灯が消える瞬間が想起されるほか、先のベチバーと共に用いることで深みを与え、そこにベチバーだけでは表現できないアミリスならではの冷たさが包み込みます。

ウッディー調の香りというのは大半が温かみのある香りとなりがちで、そうなると原曲の雰囲気が壊れてしまいます。なので、ここでアミリスを選んだ調香師に脱帽せざるを得ません。しかし、調香の完璧な部分はもう一つあります。本作3つ目の香料であり、対である作品白ミサでも中心的な香料として扱われていたラブダナムの存在です。

ラブダナムは樹脂であり、オリエンタルでねっとりとした甘さで動物的でもあり、官能的さのある香料ですが、白ミサでは性的なセクシーさとは無縁で法悦への喜びに昇華されているような調香とお伝えしました。
しかし、本作では逆に性的な妖しい甘美さを連想されるほど官能的で、本来のラブダナムらしさ満載です。それでもあくまで上品で気品を保ちながらも、そうした雰囲気を醸し出しているからこそ、あくまで悪魔崇拝の儀式である黒ミサ、原曲のスクリャービンの気品や厳かさは守られます。ここまででも充分なのに、同じメインに使っている香料一つで、このように対照的な美しい表現がとなっている調香に惚れ惚れしています。

ピアノソナタ第9番「黒ミサ」(アレクサンドル・スクリャービン)はラニュイパルファンの神髄ともいえる作品で、あえて香水にある程度精通したフレグランス中上級者の方こそ、是非お手に取っていただきたい香りです。もし、本作を初めてとった時が香水初心者の頃であったならば、トップなしに調香したり、美しすぎる調香に気づけずに、もう香りとして体験してしまったので、今のように深く感動を味わえなかったと存じます。ただし、本作を嗅いで本能的に好きになったならば、あなたが香水初心者かどうか関係なく、是非お手に取ってほしいです。
香水は恋に落ちたと思った瞬間に身にまとったからこそ見える景色もあり、それは唯一無二のものだからです。そして、その際は是非、白ミサの香りと一緒に購入されることをお勧めします。
以上がクラシック音楽の世界を表現するフレグランスメゾン、ラニュイパルファンとセレスで取り扱っている8作品の香水紹介となります。いかがだったでしょうか。何か嗅いでみたくなった、あるいは原曲を聴いてみたくなった作品は見つかりましたか?はたまた、クラシック音楽ファンの方もこちらの記事をお読みになっているかもしれませんね。
ラニュイパルファンはクラシック音楽を愛する一人のファンが自費で立ち上げた、クラシック音楽ファンを増やすべく日常的なアイテムである香水に白羽の矢を立て、厳選したクラシック音楽作曲家と選曲をしたうえで、ピアニストまで楽曲の解説に招いたり、調香師には音楽を聴かせて創らせ、自身が指揮者(コンダクター)となって先陣を切って演奏をしていく、クラシック音楽ファンは勿論、まだあまり明るくない方もクラシック音楽のことを好きになれるであろう、そんな本格フレグランスメゾンです。
秋が終わりに近づいて冬に差し掛かろうという季節になりましたが、皆様の日々の暮らしに音楽や香りを取り入れて、より良きものとなりますように。
以上、香水ライター、そしてクラシック音楽ファンの凛でした。

凛
香水を愛してやまない某IT企業Webライター。
大学の頃にラルチザンのヴォルール・ド・ローズに出会い
衝撃を受けて以来、香水愛好家となって10年以上を経る。
そのため、IT企業でのライター経験を活かし、
愛する香水のことを発信するライフワークも始める。
初恋はラルチザンのヴォルール・ド・ローズで
今の恋人はFueguia1833のChamber。
















